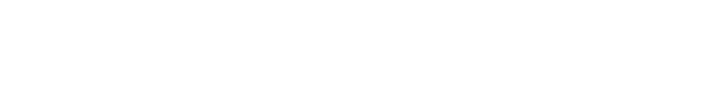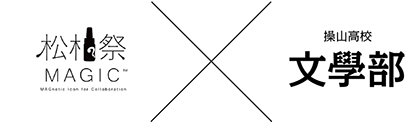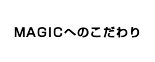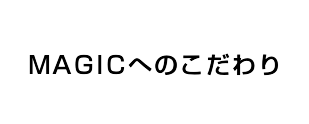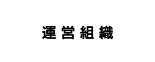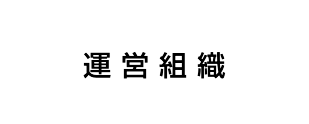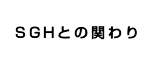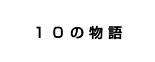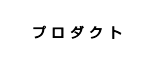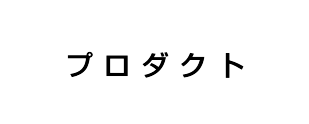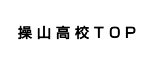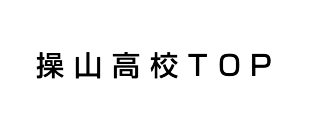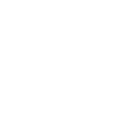
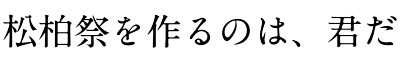

Why dont YOU GO?
龍泉華
「ねえ、ダンス教えてもらえない……?」
きっかけは友人のその言葉だったのだろう。
私はそっと目を閉じて、今日までの自分を振り返った。
Why dont YOU GO?
最初は、やや強制的な感じを覚えるテーマに呆れた。「中心に立つ人」はいつもこうだ。どうも彼らは自分たちのいかにもらしい青春のために、私のような「その他大勢」を引っ張っていきたいらしい。球技大会や宿泊研修なんかもそんな感じがしていた。
私には私のペースやテンションがあるのだから、放っておいてほしいのに。松柏祭は楽しみだったけれど、また自分が中心に立つ人に合わせなければいけないのかと思うと、うんざりだった。
私と同じような考え方の人の人は少なくなかったと思う。しかし
また、それとは全く逆の考え方の人も多く、それぞれの気持ちのギャップが生まれるのは早かった。
「みんなが言うことをきいてくれない」と泣く人、それを慰めながらもまた、その人の陰口を叩く人、それをみて「このクラスなら優勝は無理だ」と呆れる人、私たちはすぐにバラバラになった。まあしょうがない。高校生と言ったって、所詮は子ども。あのテーマの求める「融合」なんて初めからできるはずがなかったのだ。
友人が声をかけてきたのはそんな折だった。彼女はクラスの雰囲気が悪いことの一因は、自分のダンス下手さにあると責任を感じて、私に「ダンスを教えてほしい」と頼んできたのだ。確かに、周りから数テンポほど遅れている彼女は、練習の時に少し悪目立ちしていたかもしれない。でもそのせいでクラスがバラバラになるというのもおかしい、気にすることなんてないのに。そうは思ったが、仲の良い彼女の頼みを断る理由はなく、私たちは休日に集まって、1つ1つの振り付けを丁寧に復習していった。そのとき、私はそれまで適当に覚えていたダンスを、「友人に教えるのだから」と初めて一生懸命に踊ったのだ。
友人はそれまでに時間こそかかるが、一度コツを掴めると早い。何日か二人で練習すると、彼女は皆の練習にもついていけるようになり、笑顔を見せる余裕まで生まれた。クラスメイト達は「全然できていなかったあの子ができるようになっている」と驚き、それを機にクラスの雰囲気も変わり始めていた。
泣いていた人は明るい笑顔でみんなを励ますようになり、その人の陰口を叩いていた人は、なかなか振り付けが覚えられない人のサポートに回り、呆れていた人は「これなら優勝狙えるよ」と意気込んでいた。
そんな中で、私は多くの人から声をかけられた。友人からは「本当にありがとう!」と感謝され、他のクラスメイトからは「教えるの上手いんだね」なんて褒められて、最初はどう反応すればいいのかわからなくて困った。だって、今までの私は、宿泊研修のときも球技大会のときも周りに合わせる程度で、積極的にクラスに協力したことなんてなかったから。このくすぐったい感覚自体が、初めてだったのだ。でもそれは不思議と不快なものではない。だから私はもう少しそれを味わってみたくて、初めて積極的に準備に関わるようになった。
そのときから、私もまた変わり始めた。
今まであまり話したことのない人にも「おつかれ」、「ありがとう」と声をかけ、彼らもまた笑顔で「おつかれ」と返す、そういうやりとりが自然とできるようになっていたのだ。
それは、以前まで辟易していた「中心に立つ人」への偏見も薄れさせた。確かに彼らには多少強引な部分がある。しかしそれは自分のためではなくて、最前線で運営しているからこそ思う「みんなに楽しんでほしい」という強い気持ちが故だと思えたのだ。
少し積極的になるだけでこんなにも変われるのに、私はそれをしてこなかった。今までは全力でイベント事を楽しむなんてばからしいと思っていたから。いや、思うようにしていたからだ。
本当は思い切りイベントを楽しむ人を羨ましいと思いながら、私自身がそうすることを引け目に感じていただけ。「その他大勢」の私なんかが、中心に立つ素質のない私なんかが盛り上がって、いかにもらしい青春を味わうなんて、似合わない。ほどほどにやっておくのが丁度いいと。楽しむことをどこか怖がり、躊躇っていた。
でも今はちがう。「中心に立つ人」とか、「その他大勢」なんてないと知ったのだ。以前の私は、手を抜いていたからそういうことを気にしていた。けれど、一歩踏み出して全力を出してみれば、そんなことを考える余地はないし、楽しむことを怖いなんて思うこともない。
松柏祭を作るのは、他の誰でもない私たちなのだから全力で楽しめばいいのだ。今は心からそう思える。
やはり、きっかけをくれたのは友人だった。
「もうすぐスタンバイだって、ってあれ。まさか寝てた?」
「そんなわけないでしょ」
友人の呼びかけに答えながら目開けると、数分ぶりに瞳を射した陽光に思わず目が眩んだ。
「じゃあなんで目瞑ってたのよ。変なのー。ほら、行こう」
友人は笑いながら、私の手を引く。そのとき、私は自然と彼女に言いたくなった。
「……ありがとうね」
あのとき私を頼ってくれて。貴女のおかげで私は変われたよ。
そこまで言うのはやはり気恥ずかしくて、心の中に留めておく。友人はしばらくきょとんとしてから、私の心を察したみたいに微笑んで口を開いた。
「こちらこそ。松柏祭、楽しもうね」
「うん」
スタンバイ場所に行くと、暑さと緊張で真っ赤な顔のクラスメイト達がいた。お互いに「大丈夫」、「がんばろう」と励まし合っている。それは以前のバラバラだった私たちでは決してできないことで、以前の私ならばかにしていたこと。そう思うと、今日までに私たちがどれほど変わったか手に取るようにわかった。
そうしてふと自分の足元を見ると、私たちの影が柔らかく溶け合って、1つに見えた。
why don't you go?
その瞬間、大嫌いだったテーマが脳内によみがえる。今ならわか
る、このテーマが伝えたかったこと。
「それではいきます、五……」
スタートまでのカウントダウンに胸を高鳴らせて、
「……二、一、スタート!」
さあ、いこう。私たちで、全力のその先へ――