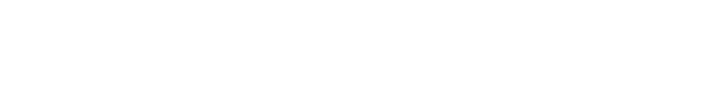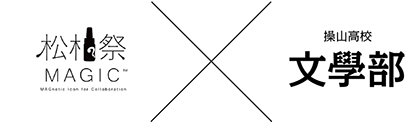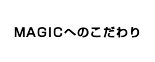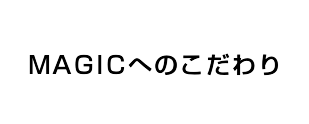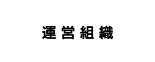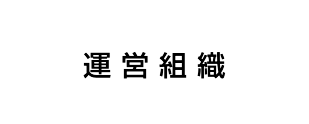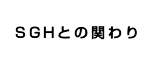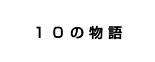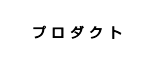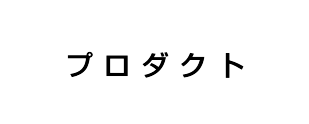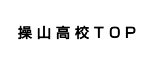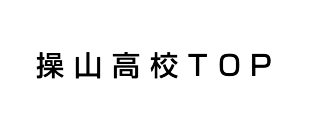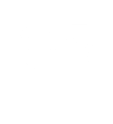
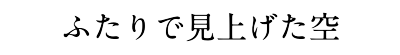

ふたりで見上げた空
水無月ふゆか
下校のピークの時刻を少し過ぎ、人も疎らになってきた校門。少女はそこに立っていた。誰かと待ち合わせをしているのだろうか。昇降口の方をぼんやりと見つめている。その瞳こそは少々熱っぽいものの、その表情は明るいとは言えない。その原因は、彼女の友人が放った何気ない一言だった。
少女には付き合って一ヶ月になる彼氏がいる。告白は彼の方からだったが、彼女も彼のことを密かに思っていたため快諾した。しかし彼の性格は天邪鬼で、少女の友人達から何度もやめたほうがいいと言われてきた。その度に何度、彼女は笑って拒否の色を見せてきただろう。
――付き合って一ヶ月にもなるのに手すら繋いでないって、逆に凄くない?
今日の昼休みに友人に言われた言葉が、少女の頭の中で渦巻く。アンタ奥手だけど手ぐらいは繋いだんでしょ? という友人の問いに、真っ赤にした顔を逸らしたときに言われた言葉だった。そうなのかもしれない、と少女は思った。付き合って一ヶ月も経つが、手を繋いだこともなければデートに行ったこともない。プラトニックというより、ままごとのような関係だ。
これは恋人としてどうなのか、と少女も流石に危機感にも似た焦燥感を抱いた。だから彼の部活がなく、一緒に帰ると約束していた今日の帰り道で、彼と手を繋ぐと決めたのだった。それでもやはり気恥しさは残る。少女は小さな深呼吸を何度かしながら、担任から急な呼び出しを食らった彼を待ち続けた。自分の気持ちと裏腹な、底抜けに青い空がやけに鬱陶しく感じた。
近くの音楽堂から吹奏楽部の心地よい音色が聞こえ始めたころ、ようやく彼が現れた。眉間にシワが寄っているところを見ると、担任の話はあまりいいものではなかったようだ。
「悪い、待たせたな。電車の時間は大丈夫か?」
少女の姿を見つけると、少年は眉間のシワを取り合って早足で駆け寄って来る。
「大丈夫だよ。行こっか」
少女は緊張を抑えながら少し無理矢理に笑顔を作って、少年と共に校門を出た。
「それで――今日図書館で見つけたホラー作家の――これが」
少年が喋る内容も全く耳に入ってこない。視線だけは彼の方を向いているが、少女の意識は彼の少し骨張った大きな手に固定されていた。並んで歩く二人の距離は約少女の手のひら一つ分。数センチぐらいのその距離が、少女にとっては千里にも感じられた。早くその数センチの千里を詰めないと、駅に着いてしまう。
「あの描写は小説――映像ではこうは――。……おい、聞いてるか?」
ずっと楽しげに本の話をしていた少年が怪訝そうに少女の顔を覗き込んだ。少女はようやく手の方に向けていた意識を少年に向ける。
実のところ、少女は少年の話を聞いていなかった。しかしそれを正直に言うとこの少年はへそを曲げて、手を繋ぐどころの話ではなくなってしまう。彼は一度機嫌を損ねると面倒くさいのだ。
「えーっと、生物で鶏の頭を解剖した話、だっけ」
「いや、そんなことは話してない」
当てずっぽうで彼の好きそうなことを挙げてみたがハズレだったようだ。
「ごめんね。ボーッとしてて」
まさか、あなたと手を繋ぎたくてその事を考えてました、なんて言えるわけがない。少女はとりあえず謝った。
これで彼の気を悪くさせてしまった。もう今日は手を繋ぐのは諦めた方がいいかもしれない。少女は気を落として少年の方を見つめた。しかし予想とは違い、彼はどこか心配そうな目でこちらを見ていた。
「あー……その、大丈夫か? 今日ずっとぼんやりしてるし、体調でも悪いのか?」
「ち、違うよ! そんなんじゃなくって……」
顔を真っ赤にして慌てて首を振る少女に、少年は「なら、いいけど……」とあまり納得していないように視線をそらした。少女は火照った顔を隠すように頬に手を当てる。
彼は普段は辛辣な物言いで悪態をつくことが多い。しかし彼女の前でだけたまに、素直な優しさなどを見せるときがある。そのことが彼女は嬉しくも、気恥しくもあった。
「で、何考えてたんだ?」
「へっ?」
少女が驚いたように顔を上げると、一転して意地が悪そうに笑う少年と目が合った。ニヤリと笑うその表情は彼によく似合う。いつもなら見惚れるところではあるが、少女の意識は少年の発した言葉の方にあった。
「だから、人の話聞かずに何考えてたんだ?」
せっかく冷ました少女の頬が再び熱くなる。少女は、その話だけは触れてほしくなかったと思いながら、何とか誤魔化そうと考えこんだ。しかしいい言い訳は一向に思いつかない。
頬を赤らめながら困ったように呻く少女を、少年は楽しげに見つめる。少年はもう、少女が自分の話を聞いていなかった事などはどうでもよくなっていた。それよりも照れ屋な彼女の見せる、困った様子を見る方が大切だった。彼は彼女の笑顔や嬉しそうな顔よりも困った顔の方が好きなのだ。そんな性格のせいで少女の友人からは酷く嫌われているが少年は何も気にしなかった。
少女はしばらくの間呻いていたが、誤魔化しきれないと思ったのかとうとうポツリと呟いた。
「…………かったの」
「えっ?」
「だからっ! 手を繋ぎたかったの……」
最後の方は蚊の鳴くような声であったが少年にはしっかりと聞こえていた。熟れたリンゴよりも赤いのではないのだろうか。少女は顔を先程よりも赤くして俯いてしまった。少年はそんな彼女を見ながら、徐々に自分の頬も熱を帯びてくるのを感じた。
照れ屋な彼女が自分からこういう事を言い出すのは珍しい。少年は確かに少々性格に難がある。しかし彼は少女の勇気や気持ちを無下にするほど性格は悪くはない。
少年は少女の小さい手を取り、そっと握った。
彼女は驚いたように顔を上げた。そして握られた手と彼の顔を何度も交互に見たあと、蕾が綻ぶように嬉しそうな笑みを浮かべた。それは少女の困った顔の方が好きだと言う少年の胸にも刺さるものがあった。先程とは打って変わり、真っ赤な顔を隠すように少年は俯いた。耳まで真っ赤にした彼を微笑ましげに見ていた少女は突然、あっ、と声を上げた。
「見て見て! すっごく綺麗な飛行機雲」
彼女のその言葉に、俯いていた少年も顔を上げ、彼女の指の先を見つめる。
二人の見上げる先には、澄んだ青空で寄り添いながら、どこまでも伸びていく二本の飛行機雲があった。