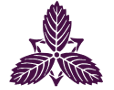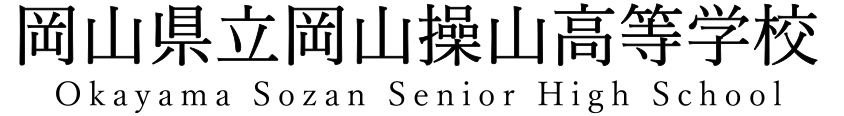サッカー
R07年度は計49名で活動をスタートしました。世界で最も愛されているサッカーというスポーツを通して見える世界が真のグローバルスタンダードという意識のもと活動しています。一昨年度末には「黒潮CAMP」という普通科進学校5校による合同合宿を行い,今年度5月には香川遠征にも行きました。県操山中学校との交流も盛んに行っています。今後も選手がスポーツを通して世界を見ることができるイベントを設定し,充実した活動を行う予定です。世界のスタンダードであるサッカーを通して見えてくる世界を一緒に見ましょう。
| 活動日 | 平日放課後,土曜(日曜) |
|---|---|
| 活動場所 | グラウンド |
| キャプテンから一言 | 学校一愛される部活動を目指して活動しています。 |














操山高校サッカー部エンブレム完成

スクールカラーの紫紺を縁取ったサッカー部のエンブレムが完成しました!
ピステやウォーマー,新ユニホームにこのエンブレムを付けています。ステッカーも作成しました。
新ユニホーム完成!!HOME(赤-白-黒),AWAY(青-青-青)
HOMEはマンチェスターU風,AWAYはチェルシー風の昇華ユニホームで番号が剥がれる心配がありません。ユニホームは個人持ちで,ストッキングもフルオーダーで選手一同気に入っています。




栄光の記録
令和6年度
- 高円宮杯CL1部所属
R6選手権ベスト28、県新人戦ベスト16
令和5年度
- 高円宮杯CL2部所属
R5県総体ベスト28
令和4年度
- 高円宮杯CL2部所属
R4選手権ベスト28
R4県新人戦ベスト28
R4県総体ベスト16
令和3年度
- 高円宮杯CL1部所属
R3選手権ベスト16
R3県新人戦ベスト16
令和2年度
- 高円宮杯CL1部所属
〇県大会出場(ベスト28)
令和元年度
- 高円宮杯CL1部所属
校誌「操山」№65より紹介
令和二年度の活動は四十九名でスタートした。新型コロナウィルスの影響での活動自粛や大会の形式変更など、部活動を取り巻く環境も著しく変容した。①中学生年代との交流、②トッププロリーグとの関わりおよびボランティア活動、③第一線で働く人からの講習会、④世界基準、全国基準の試合観戦、⑤県外チームとの交流、⑥グローカルな視点における県内普通科進学校との交流、⑦グローバルリーダー育成プログラム⑧味の素の栄養教室など、例年行われている活動が全く出来ない状況下での船出となった。そんな中でも、岡山市普通科六校戦においてはグループリーグを1位通過し、十一月下旬に優勝決定戦を迎える。また、高円宮杯U18リーグではカテゴリーを一つ上げ、八十分間の死闘に挑戦している。更に、先日行われた選手権では三回戦まで進出し、優勝校となった作陽高校との熱戦を繰り広げた。メジャーなチームスポーツにおいて、結果を出すことは難しい。やはり個々のレベルアップは必要不可欠であることをそのゲームで実感したのはもちろんのこと、チームとしての成熟度もまだまだ高みを目指さねばと痛感した年でもあった。サッカーは不確実なボールゲームである。だからこそ、この先行き不透明な時代にも臨機応変に対応していく術を、部活動に懸命に取り組むことで培っていきたい。